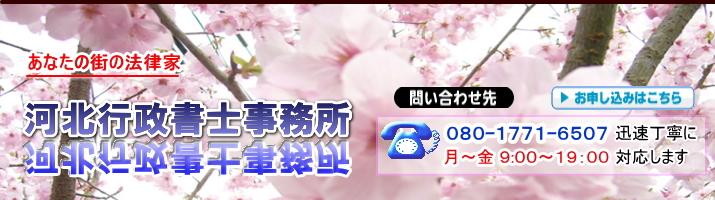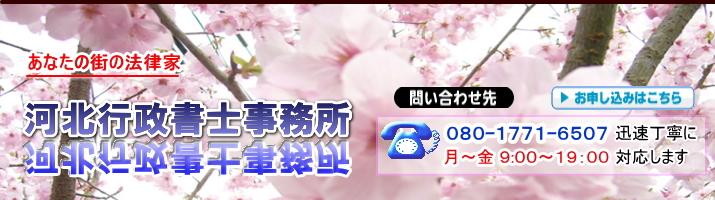|
| 二、農地法4条・5条の許可申請 |
| (1) 自分の農地を「転用」しようとする場合には、その前に知事等の許可を受けるか、 |
| 農林水産大臣の許可(4ha以上の場合(地域整備法に基づく場合を除く))を受けな |
| けければなりません(4条)。 |
| 例えば、自分の農地を転用して家を建てる場合です。 |
 |
| また、①農地の「転用」と②その農地の売買や賃貸借など権利の設定・移転 |
| を同時に行なう場合にも、4条と同様の許可を受ける必要があります(5条)。 |
| 例えば、他人の農地を購入してそこに工場を建てる場合です。 |
| |
| 但し、4条でも5条でも、市街化区域内の農地の転用については、面積の大小 |
| に関係なく、知事等の許可ではなく農業委員会への事前の届出でよいようになっ |
| ています。 |
| この届出は、許可とは異なり、受理された日から既に効力が発生しますが、 |
| 許可と同様に、届出は権利の設定、移転のための効力要件であり、かつ、登記申 |
| 請には受理通知書の添付が必要になります。 |
| なお、この市街化区域内の特例は4条、5条で認められ、3条にはありませんので |
| 注意が必要です。 |
| |
| また、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づく農用地区域内の土地の場合 |
には、原則として転用は許可されませんので、事前に農用地区域から除外する
|
| 手続き(農振除外)が必要です。 |
| 例外として、3年以内の一時転用などは農振除外は要りません。 |
 |
|
4条・5条に共通して転用を規制しているのは、農業と農業以外の土地の利用を調
|
| 整しながら、優良農地を確保して農業生産力を維持すると共に、農業経営の安定を |
| 図るためです。 |
 |
| (2) ここで規制対象である 「転用」とは、人為的に農地を農地以外のものにする全て |
| の行為をいいます。従って、一時的に資材置場などにする場合でも「転用」です。 |
| また、①地目が農地ならば、たとえ耕作していなくても、農地として扱います。 |
| ②地目が農地でなくとも肥培管理がされていれば農地とみなされ、転用には許可が |
| 必要です。 |
 |
| (3) 許可を受けないで売買契約をしたり、代金を支払ったり、引渡しを受けたりしても、効 |
| 力は生じません(同5条3項による3条4項の準用)。 |
| また、農地転用の届出前や許可前には、農地の売買契約や本登記はできません。 |
| あくまで停止条件付売買契約や売買契約の予約しかできませんし、登記も仮登記が |
| できるに止まります。 |
| 許可なく農地の転用を行った場合には、農地法違反として、工事の中止命令や原 |
状回復命令等がなされる場合があります(同83条の2)。
|
| これは無断転用をした者だけでなく、その工事等を請け負った者も命令の対象となり |
ます。
|
| 更には、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金を科せられることもあります(同 |
| 92条)。 |
 |
| (4)申請人 |
| ◇ 4条の申請の場合は、通常は、農地を転用しようとする者(農地の所有者)の単独 |
| 申請になります。 |
| ◇ 5条の申請の場合は、通常は、売主と買主(又は貸主と借主)との共同申請となり |
| ます。 |
| 例外として単独申請できる場合は、例えば以下のような場合です。 |
| ①遺贈による場合 |
| ②競売又は公売による場合 |
| ③確定判決、請求の認諾、裁判上の和解、調停、審判による場合 |
 |
| (5)権限庁(4条・5条共通) |