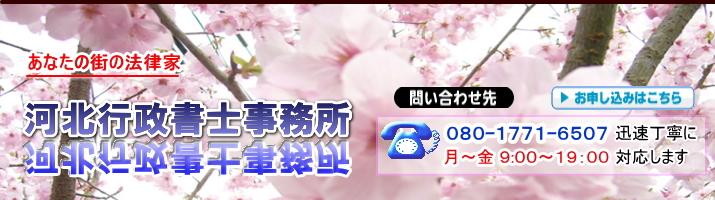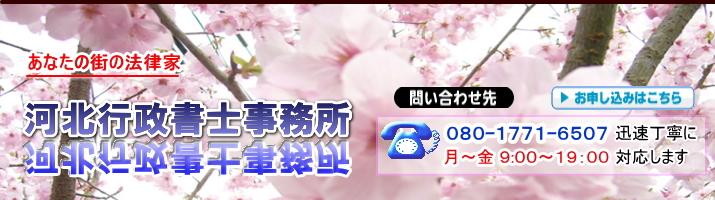| 一、 成年後見制度は、認知症や精神障害などによって判断能力が不十分な人達を保護 |
| ・支援する制度です。 |
| かなり平たく言ってしまうと、ボケが出てきたおじいちゃん・おばあちゃんが、騙されて |
| 高価な物を買わされたり、逆に、高価な物を売ってしまったりするのを防ぐための制度 |
| と思えばよいでしょう。 |
| 成年後見には、大別すると、(Ⅰ)法定後見と(Ⅱ)任意後見があります。 |
| このうち(Ⅰ)法定後見は、既に判断能力が不十分になっている人に、家庭裁判所が |
| 選んだ人を付けて保護支援させる制度であるのに対して、(Ⅱ)任意後見は、今はまだ |
| 十分な判断能力があるけれども将来判断能力が衰えてしまったときに備えて、信頼で |
| き る人にサポートしてもらう制度です。 |
| 要するに、(Ⅰ)既に判断能力がなければ、成年後見、 |
| (Ⅱ)まだ判断能力があれば、任後意見になる訳です。 |
| 両立はできません。 |
 |
| 二、法定後見 |
| 1. これは更に、本人の判断能力の低い方から、①後見、②保佐、③補助の3つに |
| 分かれています。つまり、 |
| ①いつも判断能力がない人には成年後見人が、 |
| ②判断能力がとても不十分な人には保佐人が、 |
| ③判断能力が不十分な人には補助人が、それぞれ本人に付いてサポートします。 |
| 本人の判断能力の足りない部分は補わなければならないので、それに応じて、サポ |
| ートする人の権限にも広狭が設けられています。 |
| なお、サポートといっても、料理を作ったり、介護をする訳ではありません。 |
| 本人のした法律行為に同意や取消をしたり、また本人の代理として法律行為をする |
| ことが、サポートするという中身です。 |
 |
| 2. 法定後見は本人の住所地の家庭裁判所に申立てますが、申立てできる人は決 |
| まっています。 |
| 本人、配偶者、四親等内の親族、成年後見人等、任意後見人、成年後見監督人 |
| 等、市区町村長、検察官です。 |
 |
| 3. 必要な書類は、家裁によって少し違うようですが、
|
| □ |
申立書(家裁で無料でもらえます) |
| □ |
本人の戸籍謄本、戸籍の附票、後見登記されていないことの証明書、診断書 各1通 |
| □ |
申立人の戸籍謄本1通 (本人以外が申立てるとき) |
| □ |
サポート候補者の戸籍謄本、住民票、身分証明書 (市町村長発行のもの)、
後見登記されていないことの証明書 各1通 (候補者がいる場合) |
|
 |
| 4. 費用は、 |
| □ |
収入印紙代 選択により、800円~2400円 |
| □ |
切手代 約3000円~5000円 |
| □ |
登記印紙代 4000円 |
| □ |
鑑定費用 後見と保佐では大抵の場合、医師による鑑定がありますが、
10万円前後 (家裁によって違いますが、熊本では7万円位)です。 |
|
 |
| 5. 期間は、3~4ヶ月位かかります。 |
 |
| 6. サポートする人は家裁により選ばれますが、その資格に法律上の制限はありませ |
| ん。サポート候補者がそのまま選ばれることが多いですが、法人でもいいし、複数 |
| 選ばれることもできます。 |
 |
| 7. 家裁で成年後見の審判が確定すると、成年後見の登記がされます。 |
| 以前のように、戸籍に載ることはありません。 |
| そして、限られた人が請求すれば「登記事項証明書」を発行してくれます。 |
| なぜ登記されるかというと、(Ⅰ)法定後見と(Ⅱ)任意後見に関する事項を公示し |
| て取引 の安全を図るためです。つまり、取引の相手方は自分では「登記事項証明 |
| 書」が取れませんが、本人側に「登記事項証明書」を取ってもらい、それを見せてもら |
| います。そして、そこに何も書かれていなかったら、「あ~、この人は大丈夫だ。 |
| 後で、取消されたりすることはないからな。」と安心して取引できる訳です。 |
 |